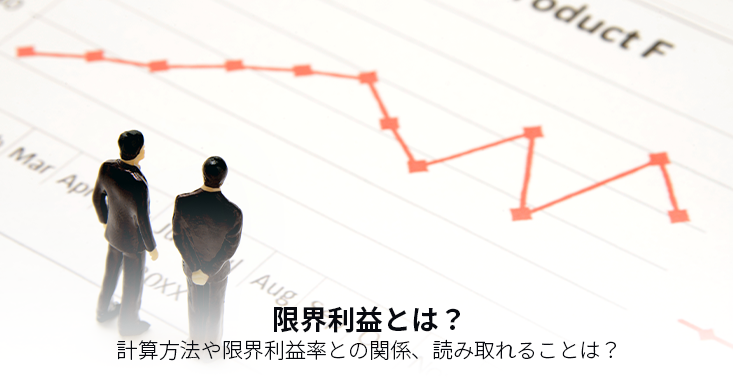請求書は紙で郵送する方法が一般的でしたが、経理業務のDXが進む昨今、請求書をデータでやりとりすることが増えています。PDF化した請求書をメールで送付したり、控えを保存したりする際は、必ずファイル名を付けなければいけません。ファイル名の付け方に決まりはありませんが、社内ルールを設け、統一することが望ましいでしょう。また、電子取引した請求書の控えを保存する場合は、電子帳簿保存法の検索要件を満たす必要があります。
この記事では、PDF化した請求書のファイル名の付け方や、メール送付する際の注意点を解説します。さらに、電子帳簿保存法に則ったファイル名の付け方なども解説しますので、参考にしてください。

目次
- 請求書にはわかりやすいファイル名を付ける
- 請求書の控えは保存するべき?
- 電子帳簿保存法における電子取引とは?
- 電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存要件
- 電子帳簿保存法の要件を満たすファイル名の付け方
- 請求書をメールで送付する際の注意点
- 安全な請求書データのやりとりには請求書発行システムがおすすめ
- 請求書発行業務のDXに取り組もう
- 請求書のファイル名に関するよくある質問
請求書にはわかりやすいファイル名を付ける
請求書のファイル名の付け方に、法的な決まりはありません。ただし、請求書に限らず仕事で使用するデータのファイル名は、内容がわかりやすいものにしておく必要があります。担当者以外が見ても、どのようなファイルなのかがすぐにわかるようにしましょう。
例えば、請求書フォルダの中に「2024年4月分」というファイル名のデータが入っていた場合、「いつの分の請求書なのか」はわかっても「どの取引先宛の請求書なのか」がわかりません。詳細を知るために都度ファイルを開かなければならず、手間がかかります。別の取引先に宛てた同月分の請求書を作ろうとして、上書きしてしまうこともあるかもしれません。
中身がわかりやすいファイル名の例には、下記のようなものが挙げられます。
<わかりやすいファイル名の例>
- 20240401_請求書_A社_◯◯プロジェクト
- 【請求書】2024年4月_A社◯◯プロジェクト
- 4月◯◯プロジェクト請求書_A社
ファイル名のフォーマットを決めたら、すべての担当者が同じようにファイル名を付けられるよう、ルールを周知します。
請求書の控えは保存するべき?
発行した請求書の控えを保存することで、未入金と入金済みのものを管理できるため、取引の状況を把握しやすくなります。しかし、請求書の控えは保存義務がないため、対応は任意です。
なお、インボイス制度に則り適格請求書(インボイス)を発行した場合は、控えの保存義務があるため注意が必要です。
請求書をPDFなどの電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の保存要件を満たす方法で保存しなければなりません。2022年の電子帳簿保存法改正前は、「メール添付で取引先に送信した請求書を印刷して、紙で保存する」といった保存方法が認められていました。しかし、法改正によって、請求書などの取引関係書類を電子的にやりとりした際、紙で保存することは禁止されています。
取引関係書類を郵送など紙でやりとりした場合は、紙のまま保存することが可能です。ただし、電子帳簿保存法では紙の取引関係書類をデータで保存することも認めています。
その際は、スキャナ保存の要件を満たす方法で保存する必要があります。スキャナ保存を行うかどうかは任意のため、必要に応じて検討しましょう。
スキャナ保存については、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
電子帳簿保存法の改正内容と2024年の対応を図解でわかりやすく解説!
電子帳簿保存法における電子取引とは?
メールで送付した請求書の控えを保存する際には、電子帳簿保存法の要件に沿った方法をとる必要があります。
電子帳簿保存法とは、国税関係書類や帳簿を紙ではなくデータで保存する場合の取り扱いなどを定めた法律のこと。電子帳簿保存法では、書類をデータ保存する際の要件を「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分けています。請求書をメールで授受した場合の区分は、電子取引です。
電子取引に該当する具体的な例には、下記のようなものが挙げられます。
<電子取引に該当する取引の例>
- メールで送信したPDFの請求書
- 請求書発行システムなどを利用してクラウド上で発行した請求書
- 電子的にFAXの送受信ができるシステムを利用して送付した請求書
- フラッシュメモリなどの保存媒体に保存して渡した請求書
請求書以外にも注文書・領収書・見積書などの取引関係書類をデータで授受した場合は、すべて電子取引に該当します。
なお、「請求書を一度印刷して押印後、PDF化してメールで送信する」といった場合、紙とデータの請求書が手元に残りますが、授受はデータで行われたため電子取引に該当します。
一方、「請求書をデータで送信した後、押印した紙を郵送。慣例として紙の請求書を原本と扱っている」といった場合は、電子取引には該当しません。
電子取引に該当するかどうかが判断しにくいときは、国税庁や担当の税理士などに確認しておくと安心です。
電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存要件
電子取引した書類をデータ保存する場合、「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。
真実性の確保は「保存されたデータが改ざんされていない正しいものであることを証明するため」、可視性の確保は「保存されたデータの内容を確認するため」の要件です。
それぞれの要件の詳しい内容は下記のとおりです。
| 真実性の確保 | 下記のいずれかを行う
|
| 可視性の確保 |
|
可視性の確保の「検索機能」については、下記の条件を満たす事業者であれば、一部またはすべてが不要となります。
<検索機能の要件が緩和される条件>
- 税務調査等で税務職員の求めに応じて書類のデータを提示、提出できるようにしている事業者は、検索機能の(2)と(3)が不要
- 前々年度の売上高が5,000万円以下の事業者の場合、同様に税務調査等で税務職員からの求めに応じて書類を提示、提出できれば検索機能のすべてが不要
なお、自社システムとは、「奉行Edge 発行請求書DXクラウド」のような請求書管理システムを指します。電子帳簿保存法に対応したシステムで、改ざん防止や検索機能が備わっています。
また、タイムスタンプを自動付与して請求書を送付するため、取引先は受領した電子請求書をそのままデータ保存するだけで電子帳簿保存法に対応できるといった点もメリットです。
電子帳簿保存法の要件については、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
電子帳簿保存法の改正内容と2024年の対応を図解でわかりやすく解説!
電子帳簿保存法の要件を満たすファイル名の付け方
前述のとおり、電子取引のデータを保存する際の要件のひとつには、検索機能の確保があります。検索機能を確保する方法は自由なため、ファイル名の付け方を工夫して要件を満たすことも可能です。
求められる検索機能は3つありますが、要件が緩和される条件にあるとおり、税務職員の求めに応じて書類のデータを提示、提出できるようにしている事業者は、検索機能の「(2)日付または金額の範囲を指定して書類の検索ができるようにする」「(3)任意の項目を2つ以上組み合わせて書類の検索ができるようにする」が不要となります。その場合、「(1)取引年月日、取引金額、取引先で書類の検索ができるようにする」を確保すれば問題ありません。
「取引年月日」「取引金額」「取引先」をすべて含んだファイル名で請求書を保存するには、例えば下記のようにするといいでしょう。
| 取引年月日 | 2024年4月1日 |
| 取引金額 | 100,000円 |
| 取引先 | A社 |
| ファイル名の例 | 20240401_A社_100000 |
出典:国税庁 PDF「電子帳簿保存法一問一答」
ただし、これだけでは請求書であることがわかりません。「20240401_A社_100000_請求書」など、ファイル名に「請求書」という書類の種類も含めるか、取引先ごとのフォルダの中に請求書フォルダを作成して、その中に保存するといった工夫をすると管理しやすくなります。
請求書をメールで送付する際の注意点
請求書をメールで送付する際は、いくつか注意しておきたいポイントがあります。トラブルを防ぎ、取引先にスムーズに内容を確認してもらえるよう、下記の注意点を確認しておきましょう。
PDFなど改ざんできない形式で作成・送付する
取引先に請求書をデータで送付する際は、PDFなど一般的に改ざんが難しいデータ形式に変換して送付しましょう。ExcelやWordのように改変が容易な形式では、取引書類としての信頼性が失われてしまいます。
内容や日付がわかりやすいファイル名にする
メールに添付する請求書名は、内容や日付がわかりやすいファイル名にします。
ファイル名は、先方がダウンロード後に変更する可能性がありますが、添付した時点でのファイル名がわかりにくいものだと、ダウンロード後の書類整理やファイル名変更の際に手間取る可能性があります。
メールで送る際のファイル名は、電子帳簿保存法の要件に則った形式でなくても問題ありませんが、開かなくても内容を推測できるファイル名を付けておくことが大切です。
請求書のデータが添付されていることをメール件名に記載する
メールの件名には、請求書データを添付したことを明記すると親切です。
重要な書類が添付されていることをわかりやすく記載し、請求書を確実に受領してもらう工夫をします。また、請求書を添付したメールの送信履歴を確認したいときも、件名がわかりやすいものになっていればメールボックスの中から探しやすくなります。
押印は廃止、または電子印鑑などに切り替える
請求書に押印している事業者は、押印を廃止するか、電子印鑑などへの切り替えを検討しましょう。
押印の有無で、請求書としての効力に変わりはありません。2020年6月に政府が押印廃止を明言したため、社印などの押印を廃止する風潮が生まれています。特に問題がなければ、廃止することで効率良く書類を作成できるようになります。慣例として押印が必要な場合は、電子印鑑への切り替えがおすすめです。
送信先の宛先の間違いに気を付ける
メールで請求書を送る際は、送信先の宛先の間違いに十分注意してください。万が一ミスがあると、外部に請求情報が漏洩してしまいます。自社はもちろん、請求先の企業にも迷惑をかけることになるため、慎重に対応しなければいけません。例えば、送信先の予測変換機能で誤ったアドレスを設定してしまい、誤送信してしまうリスクなどが考えられます。
「メールアドレスをアドレス帳に登録しておく」「メール送信ボタンをクリックする前に警告を出すシステムを利用する」など、ヒューマンエラーを防ぐシステム的な対策が求められます。
安全な請求書データのやりとりには請求書発行システムがおすすめ
安全に請求書データをやりとりするなら、請求書発行システムの活用がおすすめです。請求書発行システムとは、クラウド上で請求書の発行ができたり、取引先に送付できたりするシステムのことです。販売管理システムや会計システムと連携すれば、売掛情報(債権データ)から請求書を自動作成できます。
請求書をメールで送付する企業が多く見られますが、前述したような留意する点も多く、発行する請求書の量が多いと業務が煩雑になります。そこで、業務を効率化できる上に、ミスが起こりづらい請求書発行システムが注目されているのです。
請求書発行業務のDXに取り組もう
請求書の発行は、毎月決まった時期にまとめて処理しなければならない業務です。経理担当者の負担を軽減し、人的ミスをできる限りなくすために、請求書発行業務のDXを検討しましょう。
請求書発行システムを導入する際は、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したサービスを選ぶのがおすすめです。「奉行Edge 発行請求書DXクラウド」は、あらゆる請求書を電子化し、指定日時に自動送付することができます。インボイスの記載要件に標準で対応でき、発行した請求書の控えも自動で電子保存されます。電子請求書にタイムスタンプを自動付与するため、改正電帳法にも手間なく対応可能です。
また、「奉行Edge 発行請求書DXクラウド」は、あらゆる販売管理システムと連携するため、現在ご利用のシステムを変えることなく請求書業務のDXを実現できます。
さらに、「債権奉行クラウド」と連携することで回収予定管理や入金消込などの債権管理まで自動化でき、「商蔵奉行クラウド」と併せて利用することで、販売管理業務全体のDXが可能になります。
請求業務はもちろん、関連ソフトとの連携によって販売管理業務全体のDXにつながるため、ぜひお役立てください。
請求書のファイル名に関するよくある質問
- 電子帳簿保存法に則った請求書のファイル名の付け方は?
- 請求書のファイルをデータでやりとりした場合は、電子帳簿保存法の電子取引に該当します。電子取引の書類を保存する際は、一定の条件で検索できるようにしておかなければいけません。
税務職員の求めに応じて請求書などの書類をデータで提示・提出できるようにしておけば、「取引年月日」「取引金額」「取引先」をファイル名に含めることで、検索要件を満たせます。
- PDFの請求書をメール送信するときのファイル名の付け方は?
- 請求書PDFをメール送信するときは、内容がわかりやすいファイル名を付けましょう。
メールで送る際のファイル名は、電子帳簿保存法の要件に則った形式でなくても問題ありませんが、開かなくても取引先が内容を推測できる名前を付けておくと親切です。例えば、「20240401_請求書_A社御中」などのファイル名が考えられます。
- メールで送付した請求書の控えの保存方法は?
- メールで送付した請求書の控えを保存する場合は、電子帳簿保存法の電子取引の保存要件を満たす方法で保存しなければなりません。
発行した請求書の控えを保存することで、未入金と入金済みのものをわかりやすく管理し、取引の状況を把握できます。しかし、請求書の控えは保存義務がないため、対応は任意です。
なお、インボイス制度に則り適格請求書(インボイス)を発行した場合は、控えの保存義務があります。
- 効率的で安全に請求書をデータでやりとりする方法はある?
- 効率的かつ安全に請求書をデータでやりとりするなら、請求書発行システムの利用がおすすめです。「奉行Edge 発行請求書DXクラウド」のような、セキュリティ性が高く、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したシステムを利用すれば、簡単に請求書の電子化を進められます。債権管理や入金消込の自動化ができる「債権奉行クラウド」や販売管理業務全体をデジタル化する「商蔵奉行クラウド」と連携することで、販売管理業務全体の効率化にもつながります。

■監修者
石割 由紀人
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
関連リンク
-

請求書をペーパレス化でき、印刷から封入・送付までのすべての作業をなくせる奉行Edge 発行請求書DXクラウド
奉行Edge 発行請求書DXクラウドについて
-

あらゆる基幹システムとつながり、入金消込・債権管理の生産性を向上
債権奉行クラウドについて
-

デジタル化時代に必要な高レベルでの業務標準化とデジタル化が出来る販売管理・在庫管理システム
商蔵奉行クラウド
こちらの記事もおすすめ
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!



![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)